日本のクラフトビールは、ここ数年でぐっと存在感を増してきたと感じます。
全国各地で個性豊かなビールが次々に生まれていて、「こんなに多彩なビールがあったのか」と驚かされることも多いです。
地域の文化や自然、食材としっかり結びついているからこそ、飲むだけでその土地の空気を感じられるのが魅力だと思います。
例えば旅行先で、その土地ならではのビールを飲むのって、ちょっとした旅の楽しみの一つじゃないでしょうか。
単なるお土産じゃなくて、実際にその場で味わってこそ分かる味がある。
ビール一杯で、地元の風土や人の思いが垣間見えるって、本当に面白い体験です。
今回は、日本各地で生まれるクラフトビールに注目して、それぞれの地域ごとの特色や、いまどんなトレンドがあるのかを掘り下げてみたいと思います。
- 関連記事:クラフトビールと一般的なビールの違い>>
- 関連記事:クラフトビールとは?>>
- 関連記事:世界のクラフトビール>>
日本のクラフトビール地域ごとの特徴

日本のクラフトビール地域ごとの特徴について解説していきます。
北海道のクラフトビール
北海道といえば、やっぱり自然のスケール感が桁違いですよね。
その大地と清らかな水が、ビールにもよく表れています。
特に感じるのは「爽やかさ」。
軽やかで飲みやすいものが多く、麦の風味を活かしたホワイトエールやヴァイツェンなど、小麦系のビールがよく知られています。
個人的には、ラベンダーやハスカップを使ったビールがお気に入りです。
北海道の特産品を使ってるだけでなく、ちゃんと風味のバランスも取れていて、思わずもう一杯飲みたくなる。
大自然の中で飲む北海道ビール、最高ですよ。
東北のクラフトビール
東北のビールは、やっぱり「やさしさ」があると思います。
水がきれいだからか、全体的にスムーズで口当たりが柔らかい。
岩手、秋田、山形あたりでは、日本酒と同じ水源を使っているところもあって、どこか共通した「清らかさ」が感じられます。
あと、青森のリンゴビールは外せません。
リンゴってビールに合うの?と思うかもしれませんが、これが絶妙。
フルーティーで、でも甘すぎない。暑い夏に冷やして飲むとたまらないんですよね。
さらに、日本酒酵母を使ったビールも多くて、東北らしい融合スタイルが魅力です。
関東のクラフトビール
関東は、まさに「実験の場」って印象です。
特に東京では、新しいスタイルにどんどん挑戦していて、IPAやスタウトのような苦味や香りの強いビールが人気を集めています。
都心のブルワリーでは、海外のトレンドもいち早く取り入れていて、個性の強いビールが揃っています。
ワイン酵母を使ったり、柑橘系のフレーバーを加えたり、デザインもオシャレで洗練されている印象。
「今日はどんな味に出会えるかな?」というワクワク感があって、ビール選びが楽しいんです。
ちょっとマニアックな味に挑戦したい人には、関東のクラフトビールはぴったりです。
中部地方のクラフトビール
長野や新潟を中心に、名水を活かしたクラフトビールが揃っている中部地方。
やっぱり「水の良さ」が際立っています。
飲んだ時のクリアな感じ、口当たりの柔らかさは、この地域ならではだと思います。
静岡のお茶ビールも面白いです。抹茶やほうじ茶を使ったビールは、想像以上に香りが豊かで、後味もすっきり。
最初はちょっと驚くかもしれませんが、一度飲むとクセになります。
和の素材をここまで上手にビールに活かせるのは、さすが日本って感じですね。
近畿地方のクラフトビール
京都や大阪では、クラフトビールに「和の精神」を感じます。
抹茶、柚子、黒豆…和の素材を使ったビールが多くて、和食との相性がバツグンなんです。
抹茶ビールは特に印象的で、口当たりがまろやかでほんのり渋みがある、大人の味って感じ。
大阪や神戸のブルワリーでは、アメリカンスタイルのIPAも人気で、ガツンと苦味が効いたビールを飲みたい人にもおすすめ。
伝統と革新がうまく混ざり合っていて、飲み比べているだけで地域の個性が見えてくるのが楽しいです。
中国・四国地方のクラフトビール
この地域では、柑橘系のフルーツを使ったビールが豊富。
広島や愛媛のミカン、レモンを使ったビールは、本当にさっぱりしていて、夏場に飲みたくなる味です。
フルーツの自然な甘みと酸味が程よくて、料理との相性も抜群。
岡山の桃ビールも印象的で、フルーティーだけどちゃんと麦の味も感じられる絶妙なバランス。
ちょっと変わり種ですが、瀬戸内の塩を使った「塩ビール」もあり、ミネラル感があって後を引く美味しさ。
地元の食材と組み合わせるセンスが光ってるなと思います。
九州・沖縄地方のクラフトビールール
南国ならではのフルーツを使ったビールが揃っていて、飲むと自然と明るい気分になります。
特に沖縄のシークワーサーやパッションフルーツを使ったビールは、まさにトロピカル。
暑い日に冷やして飲むと、すごくリフレッシュできます。
そして、九州ならではの焼酎文化とビールのコラボも面白い。
焼酎の製法を応用したビールや、焼酎樽で熟成させたビールなど、他の地域にはないユニークな発想に驚かされます。
個人的には、もっと注目されていいエリアだと思います。
日本のクラフトビール市場のトレンド
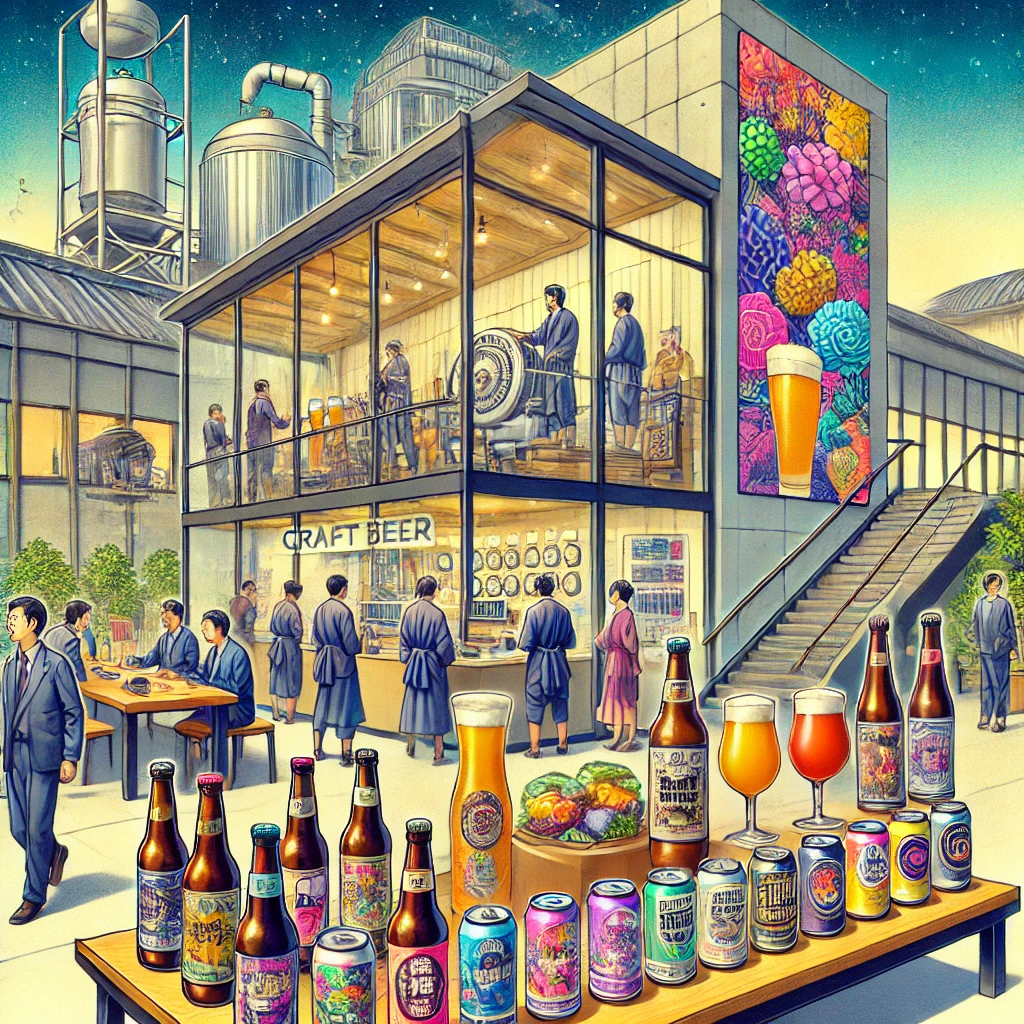
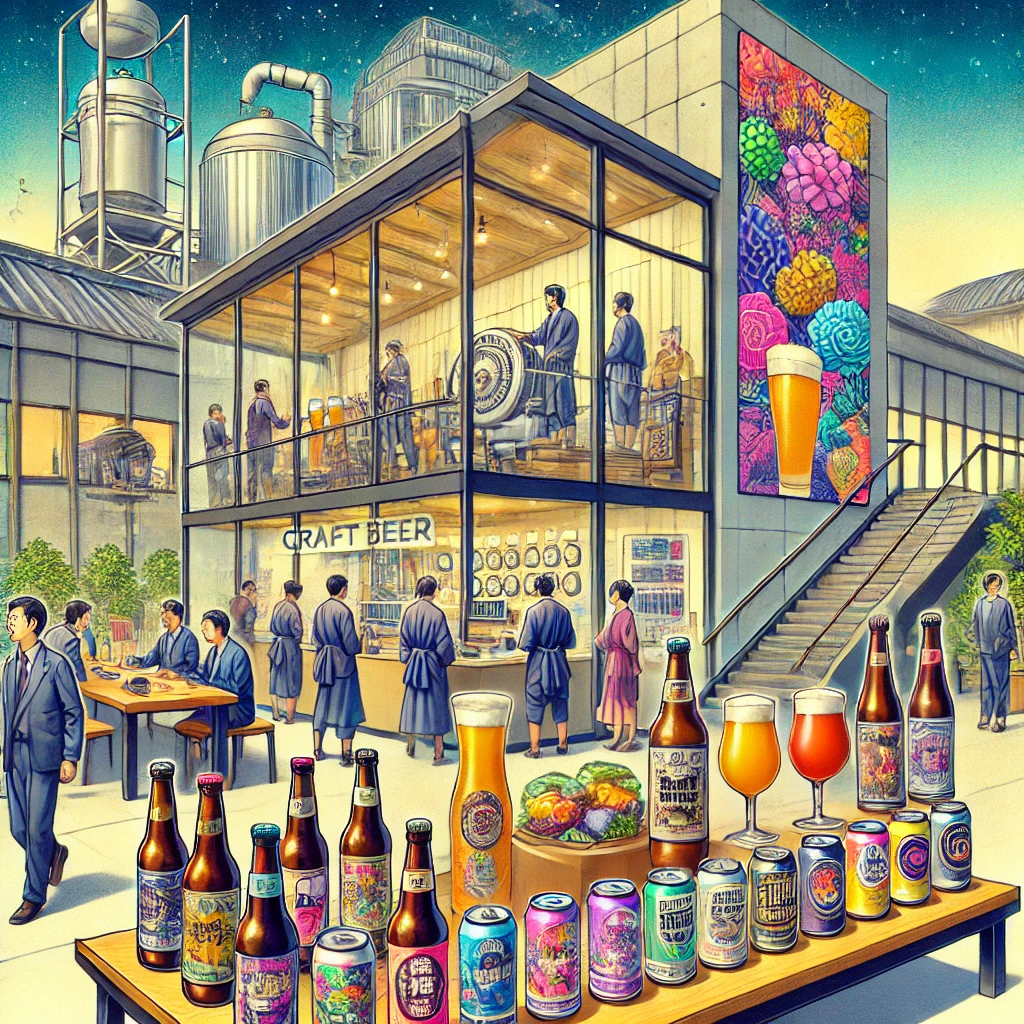
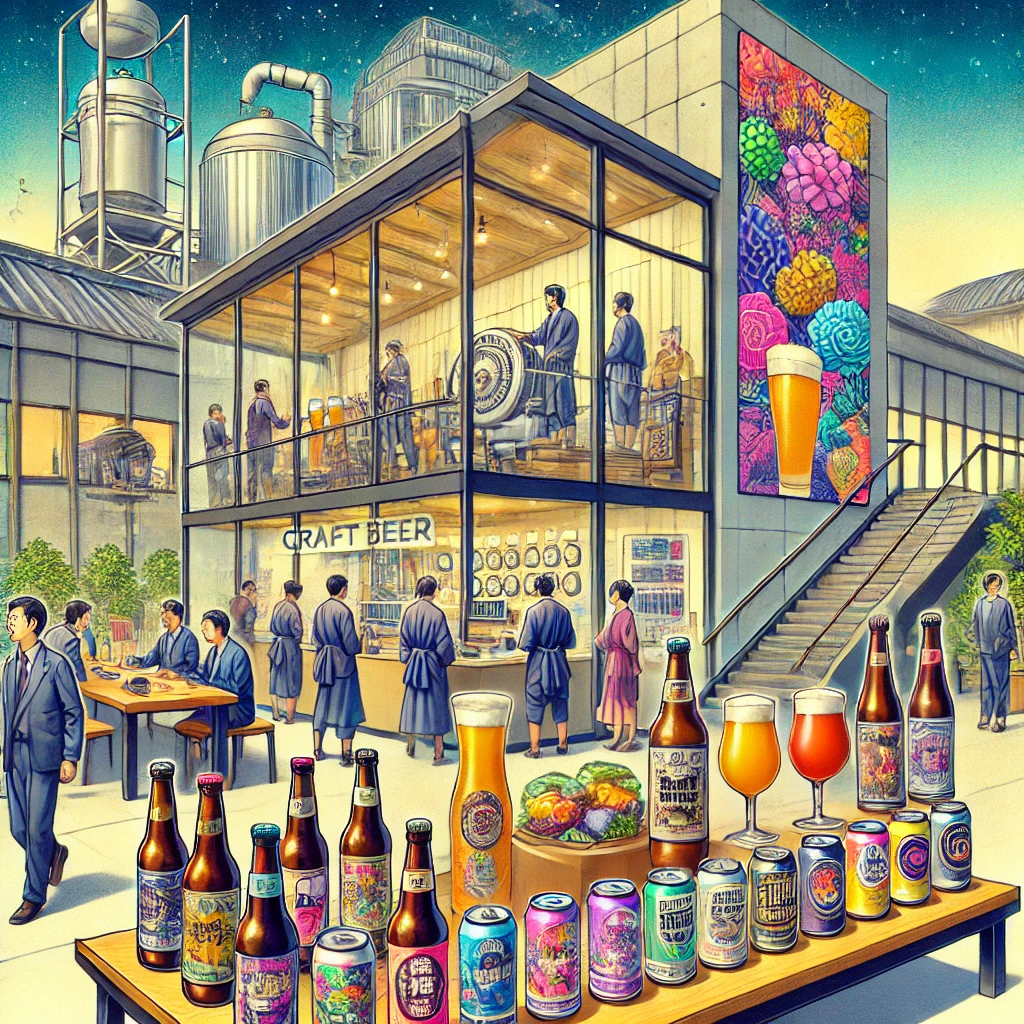
日本のクラフトビールは、ここ数年で一気に進化を遂げています。
以前は「ビールといえば大手のあの味」という固定観念が根強くありましたが、最近はまったく違います。
今のクラフトビールは、香り、苦味、酸味、コク、フルーティーさ…さまざまな味わいが楽しめるようになり、飲むたびに新しい発見があります。
実際、ひとくちに「ビール」と言っても、IPA、ペールエール、ヴァイツェン、スタウト、サワーエールなど、多様なスタイルが展開されています。
それぞれ個性があって、好みが分かれるところもまた楽しいポイントです。
私はIPAのガツンとくるホップの苦味が好きなのですが、最近は酸味のあるサワービールにもハマっています。
デザインの進化が飲む前からワクワクさせてくれる
クラフトビールの魅力のひとつは、なんといってもラベルや缶のデザインです。
おしゃれで個性的なものが多く、思わずパッケージ買いしてしまう人も多いのではないでしょうか。
気づけば冷蔵庫にカラフルな缶がずらりと並んでいて、どれを開けるか毎回迷ってしまいます。
デザインは、そのビールの世界観や味わいを表現していることが多く、アートとしても楽しめます。
SNS映えする見た目は、ちょっとした贈り物にも最適ですし、飲み会やキャンプ、ピクニックでも話題になること間違いなしです。
「食事と楽しむビール」が当たり前に
最近では、クラフトビールを料理と合わせて楽しむ「フードペアリング」が注目されています。
これまでは「とりあえずビール」だったのが、いまは「どの料理にどんなビールを合わせようか」と考える人も増えてきました。
ビールって実は、ワインや日本酒に負けないくらい奥深く、料理との相性によって味の感じ方が全然違ってきます。
たとえば、香り豊かなIPAはスパイシーなエスニック料理と相性が抜群ですし、コクのあるスタウトは、チョコレート系のスイーツや濃厚なチーズと合わせると最高です。
ペアリングを意識することで、ビールが「飲むだけのもの」から「食事を引き立てる存在」へと進化していると感じます。
若者の「自分だけの味」を求める感覚とマッチ
特に20〜30代の若い世代を中心に、「人と同じじゃつまらない」「自分の好みを大事にしたい」という価値観が強まってきています。
クラフトビールの多様性は、まさにそんな感覚とマッチしています。
「どんな味が好き?」と聞かれて、「ちょっと酸味のあるやつ」「フルーティーで軽いのがいい」と細かく答えられるくらい、選択肢が豊富です。
自分だけのお気に入りの銘柄を探す楽しさもありますし、その過程でいろんな醸造所を知ったり、地域とのつながりを感じたりすることもあります。
「このビール、○○県の小さなブルワリーが作ってるんだよ」っていう豆知識も、なんだかちょっと誇らしくなります。
地元の素材を活かしたクラフトビールが全国各地で増加中
日本各地で生まれるクラフトビールには、その土地ならではの素材が取り入れられていることが多く、まさに「飲むご当地グルメ」と言えるような存在です。
たとえば、北海道ではハスカップや富良野産ホップ、青森ではリンゴ、愛媛ではみかんといった具合に、地域の特産品を活かしたフルーツビールがどんどん登場しています。
こうしたご当地クラフトビールは、お土産や旅行中の楽しみとしても人気がありますし、実際に現地でしか飲めない限定ビールを探しに行くというのも、クラフトビール好きの間では定番になりつつあります。
味わいもその土地の風土や文化を反映していて、旅の記憶をより豊かにしてくれます。
醸造技術の進化が品質を底上げ
クラフトビールの品質は年々向上しており、日本のブルワリーの技術力には目を見張るものがあります。
特に最近では、発酵の管理や温度調整、素材の選定に至るまで、かなり細かいところまでこだわって醸造されている印象です。
その結果、飲んでいて「おいしいな」と感じる瞬間が確実に増えています。
特に、IPAやサワーといったスタイルでは、海外の有名ブルワリーにも引けを取らない味わいのものが次々と登場しています。
技術力とチャレンジ精神の両方を持ったブルワリーが増えてきたことは、日本のクラフトビール界にとって非常にポジティブな流れだと思います。
海外からの評価も上昇中
日本のクラフトビールは、国内だけでなく海外でも高く評価されるようになってきました。
国際的なビールコンペティションで賞を獲得する日本のブルワリーも増えており、その味わいの繊細さやユニークな発想が注目されています。
実際、海外のビールファンが「日本のクラフトビールを飲んでみたい」と言うケースも増えていて、日本の文化や地域性をビールという形で世界に発信できているのは本当に素晴らしいことです。
個人的には、「和」の素材を活かしたビールが、もっともっと世界で知られてほしいなと思っています。
オンライン販売で全国どこでも楽しめる
コロナ禍をきっかけに、クラフトビールのオンライン販売が一気に拡大しました。
これまでは「現地に行かないと買えない」というハードルがあった小さなブルワリーのビールも、いまではネットを通じて気軽に購入できるようになっています。
定期便サービスや飲み比べセットなども充実していて、自宅にいながらにして全国のクラフトビールを楽しむことができるようになりました。
私も何度かオンラインでビールセットを購入していますが、箱を開けるときのワクワク感はまるでプレゼントをもらったときのようです。
まとめ
| 地域 | 特徴・使用される素材 | ビールの特徴 |
|---|---|---|
| 北海道 | 北海道の大自然の恵み(例:北海道産小麦、ハスカップ) | 大自然の風味が感じられるビール。フルーティで爽やかな味わい |
| 東北 | リンゴ | 爽やかなフルーツビール。リンゴの風味が引き立つ |
| 関東 | モダンなホップ | IPA(インディア・ペール・エール)のホップ感が強い |
| 中部 | 名水(例:富士山の水) | 飲みやすくまろやかな味わい。質の高い水を使用したビール |
| 近畿 | 和の素材(例:抹茶、ほうじ茶) | 和のテイストを活かしたユニークなビール。香り豊かな仕上がり |
| 中国・四国 | 地元の特産物(例:柑橘類、ぶどう) | 地域特産のフルーツを使用したフルーツビール |
| 九州・沖縄 | 南国の素材(例:マンゴー、パイン) | 南国の風味が楽しめるビール。トロピカルな香りと味わい |
日本のクラフトビールは、ただの飲み物を超えて、「地域を知る」「味の冒険を楽しむ」「自分の好みを探す」体験そのものになっています。
全国各地のブルワリーが、それぞれの地元の素材や文化をビールに落とし込んでいるからこそ、一本一本に物語がある。
ぜひ、自分の住む地域や、旅行先でその土地のクラフトビールを味わってみてください。
そして、気に入ったものがあったら、誰かにシェアしたり、ギフトにしたりして、クラフトビールの楽しさを広げていけたら素敵だなと思います。
あなた好みの「運命の一杯」、きっとどこかで待っていますよ。
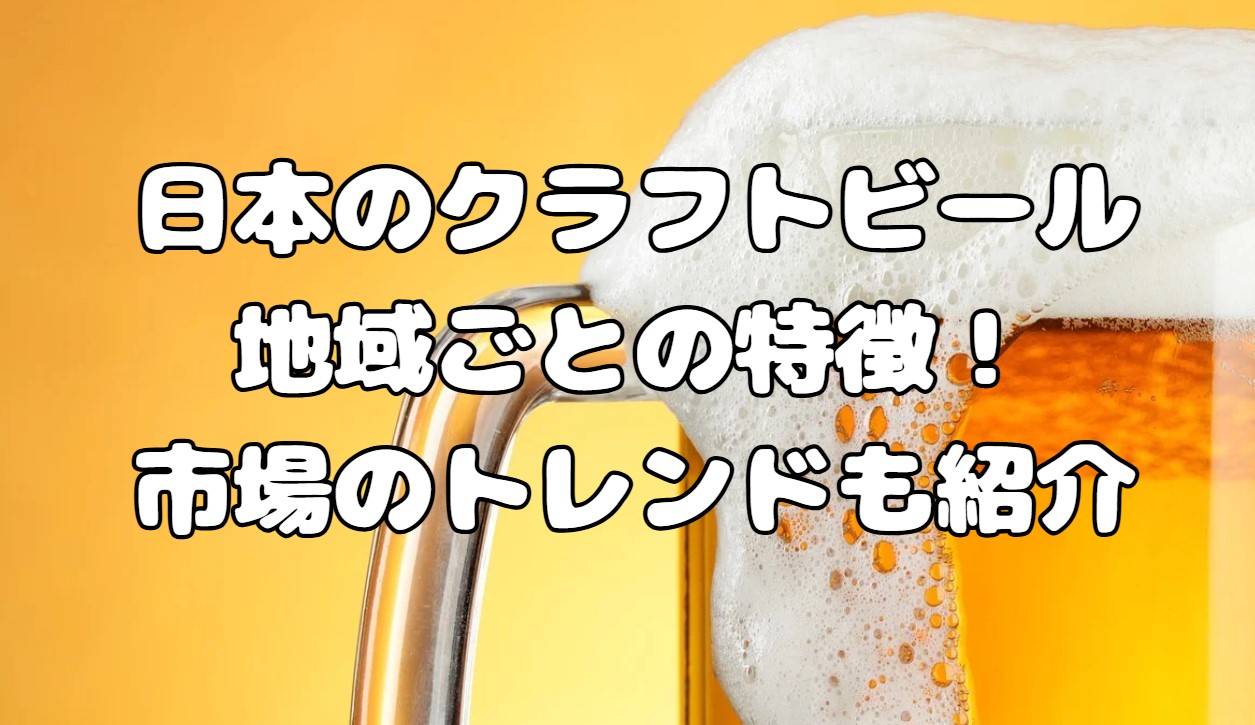









コメント